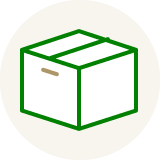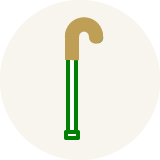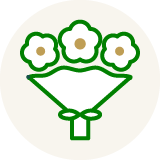令和8年度償却資産の申告について
法人や個人で事業を営んでいる場合、その事業のために所有している事業用資産(構築物や機械、器具及び備品等)には償却資産として固定資産税が課税されます。
この償却資産については、地方税法第383条の規定により、毎年賦課期日(1月1日)現在の所有者に申告が義務付けられています。
正当な理由がなく申告しない場合又は虚偽の申告をした場合は、過料又は罰金が課せられる場合があります。
市では地方税法第408条に基づく実地調査を行う場合があります。調査に伴って納税義務者や関係者へ質問を行う場合があります。
その際、申告漏れが判明した場合、追加申告をお願いすることがあります。過年度に遡って課税する場合がありますので、予めご了承ください。
詳細は「償却資産申告の手引き」をよくお読みいただき、申告書等を作成のうえ、ご提出をお願いします。
昨年度までに申告されている方や新たに償却資産の所有が見込まれる方には申告書類又は案内ハガキをお送りしています。
申告される方は必要な書類をお送りしますので、税務課資産税係までご連絡ください。
提出期限
令和8年2月2日(月曜日)まで
法定の申告期限は1月31日ですが、事務処理の都合上、1月19日(月曜日)までに提出してください。また、1月1日時点での資産の状況を申告していただくため、12月中の申告書の提出は受付できませんのでご注意ください。
eLTAXを利用した電子申告のご案内
申告書の提出は便利な電子申告をご利用ください。
- インターネットを利用して、自宅やオフィスなどから簡単に申告ができます。
- 紙の申告書作成よりも手間がかかりません。
- 複数の地方団体に資産が所在している場合でも、一括でそれぞれの地方団体分の申告書を作成・送信することが可能です。
詳細はeLTAXホームページをご確認ください。
償却資産申告書へのマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載について
平成28年度より、償却資産申告書へマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載が義務付けられています。
詳細は下記にてご確認ください。
受付印を押印した控えについて
郵送で提出される方で、申告書に押印した控えが必要な場合は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。
なお、市からお送りした申告書以外でご提出される方は、記載された申告書をコピーしていただき、提出用と控用をご用意ください。
課税標準の特例について
固定資産にかかる課税標準の特例適用には申告書の提出が必要となります。
詳細は下記にてご確認ください。
見落としがちな資産
事業の用に供することができる状態であれば申告が必要です。
- 建設仮勘定で経理されている資産
- 簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)
- 償却済資産(減価償却が終わった資産)
- 遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)
- 未稼働資産(既に完成しているが、未だ稼働していない資産)
- 改良費
- 家屋として評価されない建物
- 借用資産(リース資産)で、契約の内容が割賦販売と同等である資産
- 取得価額が30万円未満の資産で、租税特別措置法の規定により即時償却した資産
- 福利厚生施設で使用されている資産
よくある質問
現在使用していない資産は申告の対象になりますか
「事業の用に供することができる」状態であれば申告の対象です。他にも、既に完成しているが稼働をさせていない資産についても、同様に申告の対象となります。
資産の評価に最低限度額はありますか。耐用年数の過ぎた残存簿価1円まで減価償却された資産は申告の対象になりますか
固定資産税における評価額の最低限度額は、取得価額または改良費の額の5%に相当する額とされています。
国税においては備忘価額(1円)まで減価償却が認められていますが、地方税では、その資産が事業の用に供することができる状態におかれている限り、課税客体となります。
補助金を使って設備導入したが、申告時の取得価額は、もとの金額から補助金を引いた金額でよいか
補助金を引く前の、もとの金額で申告をしてください。地方税では圧縮記帳は認められていません。
会社を廃止・閉鎖した場合は、申告は必要ですか
廃止・閉鎖した旨を申告していただく必要があります。その際には、申告書の備考欄「閉鎖・廃業・解散・転出等」で該当する箇所を○で囲み、その日付を記載してください。
取得価額を算定する際に、消費税はどのように取り扱えばよいですか
法人税または所得税の会計処理において、税抜経理方式を採用している場合は消費税を含まない金額、税込経理方式を採用している場合は消費税を含んだ金額となります。
家庭用にも事業用にも使っている備品等は申告の対象ですか
事業の用に供している資産であれば、申告の対象です。
なお、一つの資産に対し、家庭用部分と事業用部分で按分して取り扱うことはできません。
税務会計上、減価償却を行っていない資産や簿外資産は申告の対象ですか
減価償却を行っていなくても、その資産が「事業の用に供することができるもの」であれば、申告の対象です。
自動車は償却資産の申告の対象ですか
自動車税の種類割の課税対象となる自動車及び軽自動車税の種別割の課税対象である軽自動車は、償却資産の課税対象ではありません。
なお、トラクターやフォークリフト等の小型特殊自動車は軽自動車税(種類別)の申告が必要です。
設備の耐用年数を知りたい
耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」により定められています。詳細は国税庁のホームページに掲載されています。
中古資産の耐用年数を知りたい
中古資産は既にある程度の年数に渡って事業の用に供しており、通常の法定耐用年数を適用することが妥当でないと判断される場合もあります。そこで、購入者が使用可能である年数を見積もり、その年数を耐用年数とすることができます。
また、使用可能年数の見積もりが困難な場合は「簡便法」により耐用年数を求めます。詳しくは国税庁ホームページに掲載されています。
取得価額が不明な場合、どうすればよいですか
同種の資産を新品で取得した場合いくらかを計算し、それから経過年数に応じた減価を控除した金額を取得価額(再取得価額)とします。
なお、再取得価額が不明な際は、推定取得価額を取得価額とします。推定取得価額は、資産再評価の基準の特例に関する省令第2条または第3条に規定されています。
帳簿の提出や実地調査の依頼が届きました。どうすればよいですか
新城市では地方税法第353条および408条に基づき、賦課漏れ資産や評価の誤り等がないかを確認し、適正な課税事務を遂行するため、帳簿の提出依頼や実地調査を行っています。固定資産台帳・減価償却計算書などの帳簿内容と、申告内容の確認をさせていただいておりますので、ご協力をお願いします。
償却資産について、国税(法人税・所得税)と地方税(固定資産税)の取扱の違いを教えてください
主な違いは以下の通りです。
| 項目 | 固定資産税 | 国税 |
|---|---|---|
| 償却資産の基準日 | 賦課期日制度(1月1日) | 個人:暦年 |
| 減価償却の方法 | 原則、定率法 | 定率法または定額法の選択制度 |
| 前年中の新規取得資産 | 半年償却(1/2) | 月割償却 |
| 圧縮記帳 | 認められません。圧縮前の取得価額としてください。 |
認められます。 |
特別償却 |
認められません。 |
認められます。 |
| 評価額の最低限度 | 取得価額の5% |
備忘価額(1円まで) |
| 改良費 | 区分評価 | 原則、区分評価 |
| 中小企業者の少額資産の損金算入の特例 | 認められません。 | 認められます。 |
| 自動車 | 大型特殊自動車のみ申告対象 | すべて減価償却費の対象 |
| 家屋 | 固定資産税(家屋)の課税対象とならないもののみ申告対象 | すべて減価償却費の対象 |
| 項目 | 固定資産税 | 国税 |
|---|---|---|
| 少額の減価償却資産 | 一時損金算入されたものは申告対象外 | 使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満のもので、一時損金算入しているもの |
| 一括償却資産 | 申告対象外 | 減価償却資産(取得価額が10万円以上20万円未満)を一括償却して、3年で損金(必要経費)しているもの |
| 個別償却資産 | 金額にかかわらず申告対象 | 個別償却しているもの |
| 租税特別措置法を適用して取得した30万円未満の減価償却資産 | 申告対象 | 租税特別措置法における中小企業者等の特例制度により、損金(必要経費)算入しているもの |