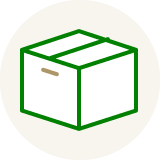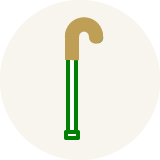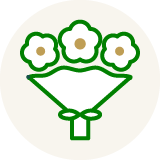長篠・設楽原の戦い
設楽原を舞台として繰り広げられた長篠・設楽原の戦い。織田・徳川連合軍と武田軍、新旧戦術の戦いが歴史を大きく動かすことになりました。
日本各地に有力な戦国大名が郡雄割拠するこの時代、奥三河には、山家三方衆と呼ばれる土豪がいました。東に今川・武田、西に織田・松平などの有力大名に囲まれたこの地では、自家の存続のため、めまぐるしく従属関係を変えなければならず、時には親子が敵味方に分かれて戦うこともありました。天正3年(1575年)、奥平貞昌が徳川氏の家臣として長篠城に入ったことから、歴史は動きだします。
その城をめぐって繰り広げられた織田・徳川連合軍の鉄砲と馬防柵、武田の騎馬隊の戦いは、斬新な戦術を追求した信長と、伝統的な戦術に秀でた勝頼との激突であり、新旧の戦術がこの地で対決しました。この戦いの勝利後、奥平家は新城の地に移り城を築き、新城城主として新城の町の礎を築きました。
長篠城跡
永正5年(1508)に菅沼元成が築いた長篠城は、豊川と宇連川の合流点に位置し、北方に人口の堀と土塁を築いた堅固な城でした。戦国の世の常として、今川、武田、徳川にと帰属を変え、天正3年には21歳の奥平貞昌が城主となりました。この城を長篠・設楽原の戦いで武田信玄の子・勝頼が父の上洛の夢を果たそうと15,000人の大軍により包囲しましたが、貞昌は500人の兵で籠城に耐え抜きました。
設楽原古戦場
天正3年(1575)、長篠・設楽原の戦いの舞台となった場所。武田軍と織田・徳川連合軍の総勢5万人を超える兵士達が、当時東西の勢力の要となっていた長篠城をめぐり様々な戦術を駆使して戦いました。無敵を誇っていた武田軍の騎馬隊に対する織田・徳川連合軍は、「火縄銃」という新たな武器を「鉄砲隊」と「馬防柵」という戦術で組織的に利用し、圧倒的な強さで短期間の内に決戦を征しました。その馬防柵が決戦場跡に再現されています。
城跡などを辿る
新城城跡
長篠・設楽原の戦いの結果、織田・徳川連合軍の大勝利に帰したので、奥平貞昌は、信長の信の一字をもらって信昌と改め、家康の長女・亀姫をめとり、天正4年(1576)に新城城を築城しました。
野田城跡
元亀4年の戦いの際、信玄が鉄砲で撃たれたという話が伝わっています。
城内にいた笛の名人、村松芳休の奏でる笛の音に、夜、信玄が聞き惚れて堀端に出たところを鉄砲の名人、鳥井半四郎に撃たれたということです。これが原因かどうかはわかりませんが、信玄はこのころから病気になり、帰路の途中、信州駒場で死んだとされています。
古宮城跡
元亀3年(1572年)に奥平氏の監視のために武田信玄の重臣馬場美濃守信春が甲州流の縄張りで、武田軍の最前線基地として築城。2年後奥平・徳川連合軍の前に自焼陥落しましたが、名城の面影を今に残しています。
亀山城跡
応永31年(1424年)に奥平貞俊によって築城された。周辺には、武田方によって築城された古宮城や寒之神神社があります。