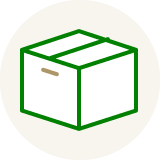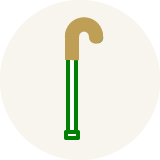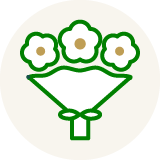馬背岩(うまのせいわ)
種別
国指定天然記念物(地質・鉱物)
指定年月日
昭和9年(1934年)5月1日
所在地
新城市豊岡字中杉上(宇連川河床)
内容
この岩脈は、おおよそ1500万年前に奥三河地域一帯で大規模な火山活動がありました。その後半、断層運動でできた南北の大地の割れ目が無数にでき、そこに安山岩質の溶岩が次々と流れ込みました。
宇連川の河床を形成する凝灰角礫岩は長い年月に亘って浸食を受けたが、この安山岩は周囲より盛りあがった形状で残り、その姿が「馬の背中のタテガミ」のように見受けられたことから、「馬背岩」と呼ばれている。
この岩脈の大きさは長さ122m、幅2.9mから6.3m、高さ約7mの大きさを測り、この種の岩脈の最も標式的なものである。
宇連ダム周辺には、数キロにも及ぶ岩脈がいくつも存在します。「馬の背岩」は規模からすると小型の部類になりますが、湯谷という観光地のひときわ目立つ場所であるため、多くの人が訪れることができる岩脈です。
参考文献
- 「目で見る鳳来町の文化財」 平成元年 鳳来町教育委員会
- 「鳳来町文化財ガイド」 平成10年 鳳来町教育委員会
その他
宇連ダム周辺には、数キロにも及ぶ岩脈がいくつも存在します。また、上流部には大ポットホール(名号池)も見られる。
お問い合わせ
新城市 教育部 生涯共育課 設楽原歴史資料館
電話番号:0536-22-0673
ファクス:0536-22-0673
〒441-1305 愛知県新城市竹広字信玄原552番地