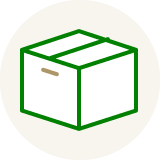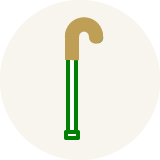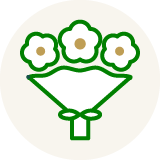令和6年10月1日から、児童手当の制度が一部変更になりました
令和6年10月より児童手当制度が改正されました。
制度改正については、以下のリンク先のページをご覧ください。
よくあるお問い合わせ
児童手当について、お問い合わせの多い質問をまとめました。
令和7年度現況届
現況届は毎年6月1日の養育状況を把握し、引き続き児童手当を受ける要件を満たしているかを確認するためのものです。提出が必要な方には、必要書類を郵送しましたので必ずご提出ください。
児童手当制度
この制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。
手当を受給できる方
児童手当は、以下の要件のすべてに該当する方が受給できます。
- 日本に住所がある
- 日本に居住している高校生年代まで(18歳到達後最初の年度末まで)の児童を養育している父または母のうち、生計の中心者の方
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても上記条件を満たしていれば受給できます。
- 離婚協議中や離婚後で、父母等が別居している場合は、児童と同居している方が優先的に受給できます。
- 児童が施設に入所している場合や里親等に預けられている場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当が支給されます。
- 公務員の方は、勤務先にお問い合わせください。
支給額(1人当り月額)
児童の年齢 | 第一子及び第二子 | 第三子以降 |
|---|---|---|
| 0歳から3歳の誕生月まで | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳から高校生年代まで | 10,000円 | 30,000円 |
| 大学生年代(18歳年度末から22歳年度末) | 子の数のカウントのみ | 子の数のカウントのみ |
※第三子以降とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※高校生年代以下の子の人数に19~22歳年代の子の人数を加えても3人未満の場合は、支給額に影響はありません。
手当の支給日
年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に分けて、2ヵ月分ずつ支給します。
原則5日に支給しますが、土日祝日の場合はその前日に支給します。
- 2月5日(12月から1月分)
- 4月5日(2月から3月分)
- 6月5日(4月から5月分)
- 8月5日(6月から7月分)
- 10月5日(8月から9月分)
- 12月5日(10月から11月分)
児童手当の支給は、市役所で申請した日の属する月の翌月から開始(一部特例あり)され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
主な手続き
現況届
毎年6月に養育状況等を確認するため現況届を提出いただいてましたが、令和4年度より現況届の一律の提出義務を見直し、届出により届けられるべき内容を公簿等によって確認できる方は、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、引き続き現況届の提出が必要な方(公簿等で確認できない方)につきましては、現況届の提出がなければ手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
引き続き現況届の提出が必要な方(現況状況を公簿等で確認できない方)
- 法人である未成年後見人や施設等受給者
- 同居父母のうち6月1日現在で配偶者と離婚協議中の方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童と別居している方
- 大学生年代の子に係る「監護相当・生計費の負担についての確認書」の児童の職業欄を学生以外で提出された方
- その他養育状況を確認する必要がある方
提出書類
- 児童手当現況届(対象となる方に郵送します)
※この他にも受給者の状況に応じて、書類の提出を求めています。
認定請求書
- 第1子が生まれた場合
- 他の市町村から新城市へ転入してきた場合
※公務員(独立行政法人にお勤めの方を除く)の方は、勤務先で手続きをしてください。
※お子さんが生まれた方は出生日の翌日から、新城市に転入された方は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きをしてください。
手続きが遅れると、手当の支給開始が遅くなる場合があります。
申請に必要なもの
- 児童手当認定請求書(用紙は窓口にあります)
- 請求者名義の普通預金通帳
- 請求者、配偶者のマイナンバーの分かるもの(通知カード、マイナンバーカード等)
- 身元確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 請求者の保険証や資格確認書(国家公務員共済、地方公務員共済に加入されている方のみ)
例:国立大学法人の職員、日本郵政共済組合 - 別居児童のマイナンバーの分かるもの(児童が市外に住所がある場合)
※この他にも受給者の状況に応じて書類の提出を求めています。
※添付書類は後日提出することもできます。
額改定認定請求書
- 支給対象児童が増えた場合(出生など)
- 支給対象児童が減った場合(離婚や施設入所など)
※お子さんが生まれた方は出生日の翌日から、新城市に転入された方は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きをしてください。手続きが遅れると、手当の増額開始が遅くなる場合があります。
変更届
- 受給者と児童が別居した場合
- 振込先の口座を変更したい場合(受給者本人名義の口座への変更に限る)
- 配偶者が公務員になった場合
- 被用者・非被用者の区分が変更になった場合
受給事由消滅届
- 受給者が他の市区町村に転出した場合
(転出先の市区町村では、認定請求手続きが必要です) - 支給対象児童がいなくなった場合(離婚や施設入所など)
- 受給者が公務員になった場合
(勤務先では、認定請求手続きが必要です)
4月分以降の第三子加算
養育する子が3人以上いる受給者のうち、以下に該当する方は3月末で加算期間が満了します。4月以降も引き続き養育される方は、手続きが必要です。
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出した方のうち、記載した子(22歳を除く)がこの3月末に専門学校等を卒業予定の方
- 高校年代でこの3月末に卒業予定の年代の方
いずれも、就職等により父母が養育しない場合や養育する子が3人未満の場合は手続きはありません。支給額の改定通知書を送付します。
手続きが必要な方には、申請案内を送付します。対象となる方で申請案内が届かない場合は、お問い合わせください。
よくあるお問い合わせ
お問い合わせの多い質問をまとめました。
出生届を出したが、児童手当の手続きは必要ですか?
出生届を提出しただけでは、児童手当は支給されません。出生日の翌日から15日以内(15日目が市役所の閉庁日の場合は、その翌開庁日)に手続きをしてください。児童手当は遡って受給できませんので、手続きが遅れないようご注意ください。
なお、手当を受給する方が公務員の場合は勤務先での手続きになります。
里帰り先で出生届を出したが、児童手当はどこで手続きしますか?
手当を受給する方の住所地(公務員の場合は勤務先)で手続きしてください。住民票ができるのが出生日の翌日から15日を越えてしまいそうな場合は、里帰り先に提出した出生届の控えや母子手帳など出生日を証明するものをお持ちください。
公務員になった場合、手続きは必要ですか?
新城市からの支給資格は無くなり、勤務先から児童手当を支給します。採用辞令または写しを持って来庁ください。手続きが遅れると手当を返還していただくことがあります。ご注意ください。勤務先では、採用日の翌日から15日以内に手続きを行ってください。
公務員を退職する場合、手続きは必要ですか?
職場からの支給資格は無くなり、新城市から児童手当を支給します。退職日の翌日から15日以内(15日目が市役所の閉庁日の場合は、その翌開庁日)に退職辞令または写し、通帳等を持って来庁ください。児童手当は遡って受給できません、手続きが遅れないようご注意ください。勤務先には受給資格の消滅手続きを行ってください。
市外へ転出しますが、手続きは必要ですか?
受給者が他の市町村へ転出すると新城市からの支給資格は無くなるため、手続きが必要です。転出先では、転出予定日の翌日から15日以内に手続きを行ってください。学業等の都合により児童や配偶者のみ転出する場合は、引続き児童を監護(生活費の送金、日常的な連絡等)する状況の申立手続きが必要です。
受給者を配偶者に変更できますか?
児童手当は、前年の所得や健康保険の適用状況等を考慮し生計を維持する程度の高い方に支給します。配偶者が生計を維持する程度の高い方となった際は、手続きをすることで受給者を変更することができます。
氏名が変わった場合、手続きは必要ですか?
児童手当の振込先である金融機関の名義を変更した場合は、手続きが必要です。名義を変更した後の通帳又はキャッシュカードをお持ちください。金融機関の名義変更をしない場合は、引き続き手当の振り込みができるため手続きはありません。
児童手当の振込先を配偶者名義の口座に変更できますか?
原則、児童手当は配偶者やお子さん名義の口座へ振り込むことはできません。ただし、離婚協議中により受給者と別居している場合は、子どもと同居している保護者が手当を受給できますので、次の質問をご確認ください。
離婚を前提とした別居を考えています。受給者を変更できますか?
現在の児童手当受給者と配偶者が住民票上別居であり、配偶者と児童が同居していること。離婚協議中であることがわかる書類(離婚裁判に係る控訴状の副本や離婚申立てにかかる内容証明郵便の謄本等)を提出できること。以上の要件を満たす場合は、受給者を切り替えることができます。
受給者が亡くなった場合、どのような手続きがありますか?
亡くなられた受給者に未支払い分の手当があるときは、支給対象児童のうち最も年長の児童に支給します。支給手続きを行うため、児童の通帳等をお持ちください。また、今後の手当について児童を養育する方に支給しますので、養育する方の通帳等もお持ちください。
※いずれも、受給者が公務員の場合は勤務先での手続きになります。
ぴったりサービス(電子申請)での手続きについて
国のマイナポータルを利用したぴったりサービスによる電子申請が可能です。申請方法等は下記ぴったりサービス(外部サイト)からご確認ください。
※電子申請を行うためには住所、氏名等の券面情報が最新のマイナンバーカード及びパソコンとICカードリーダーまたはマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンが必要となります(手続きにおいて署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書、券面事項入力補助用の各暗証番号が必要)
※別途、添付書類が必要な場合があります
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 こども未来課
電話番号:0536-23-7622
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階