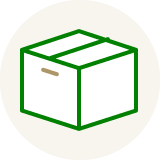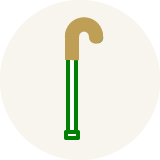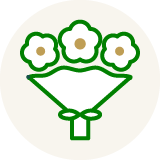五平餅は奥三河のみならず、中部地方の各地に伝わっています。その味や形は地域によってさまざまです。
新城市では少し甘めの赤みそ味でわらじのような形が多いですが、ほかの地域ではみそにすりつぶしたクルミなどを入れた甘い味付けや、醤油ベースの味付けで、形は3色団子のような団子型や丸型だったりします。
新城市には「五平餅」が古くから伝わっています。五平餅は社会生活や環境が変化し、豊かな食生活に満たされている現代でもなお愛され、食されています。
このふるさとの味五平餅は、「山の講」という農民の山の神の信仰から始まったといわれています。山の神は、春になると山から麓に下ってきて実りを見守り、豊穣の守護神となり、秋の収穫が終わると再び山に帰っていきます。山で働く者は、山仕事にかかるのに先立ち、旧暦2月と11月(10月の場合もある)の山の神の祭日に、五平餅などを作っておそなえをし、おまつりしていました。この山の神様をおまつりすることを「山の講」といいます。
五平餅の名前の由来は、その形が神前の「御幣」に似ていることからといわれています。五平餅は、白米を炊いてつぶして、杉の木の串に平たい形に押しつけ、あぶります。神前には白いまま少しあぶって献上します。「お下がり」をいただくときには甘い練りみそをたっぷりつけて、さらにあぶります。杉の木の香りとともに香ばしい焼けたみその風味がよく、食欲をそそります。
備考
五平餅の起源は、ほかにも「五平さん考案説」など諸説あり、正確な説は定かではありません。